まずは自己紹介をさせてください。gugusukeと申します。

現役の今でもわたしの必需品はアルゴリズムとフローチャートです。
成功するコツはフローチャート
文系出身者の研修で心が折れそうになった時に救ってくれたのがフローチャートでした。
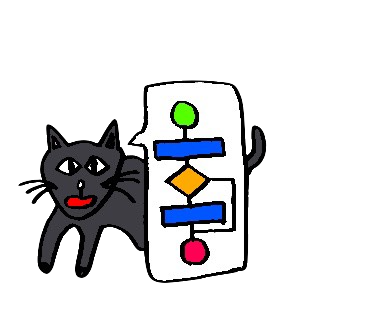
それから現在に至るまで、仕事をするうえでわたしの中で必須スキルとなっています。
アルゴリズムの考え方
アルゴリズムとは、「問題を解決するための手順や手法」のことを指します。
詳しく知りたい方は「アルゴリズム」で検索していただくと詳しく説明しているサイトがいくつもあると思いますので、そちらをみていただくと良いかと思います。
一言で表すならばスタートからゴールまでのプロセスだと思っています。
そのゴールを導くための手法の1つにフローチャートというものがあるのですが、これがわたしが研修を乗り越えるために身につけた必勝法になります。
フローチャートが活躍したきっかけ
では、実際にフローチャートがどんな場面で活躍したのかを説明していきます。
わたしが入社した企業では研修の序盤にフローチャートについて軽く勉強しましたが、プログラムを実際に組むための研修がほとんどでした。

最初は代入や計算といった簡単なプログラムだったので、なんとかついていくことができたのですが、判定文や繰り返し文といった今では当たり前に使っていることが最初の壁でした。
この時のわたしは、周りの同期の人たちがすらすらとプログラムを書いていたのに焦っていたこともあり、いきなりプログラムを書いていました。
その結果、何をどうしたら良いかがわからないまま作ったプログラムは正しい動作をすることはありませんでした。
心が折れかけていた時に、同期の一人から「頭の中でフローチャートを考えているよ」とアドバイスをいただきました。
いきなり頭の中でフローチャートを考えることは難しかったので、ノートに書き出してみました。

アドバイス通り実行してみました。
するとスタートからゴールの間に何をしなければいけないのかが見えてくるので、それをプログラムに書いていくという説明書のようなものができたのです。
研修でやったフローチャートがこんなところで役に立つとは思ってもいませんでした。
それ以降、まずはフローチャートを作ってからプログラムを書いていくことで、スタートからゴールまでのプロセスがわかるようになり、研修を乗り切ることができました。
簡易的なフローチャートで良い
フローチャートをネットで調べると図形(フローチャート記号)が出てくると思いますが、これを覚える必要はないと思っています。
プログラムを作成するうえでフローチャートを提出することはほとんどないと思うので、自分のわかるように描くことが大事だと思っています。
わたしは転職を2回しており、さらにいくつもの現場を経験してきましたが、フローチャートを作成する現場はありませんでした。
わたしは下記の図形は使用していますが、その他は適当な図形を使っています。
実処理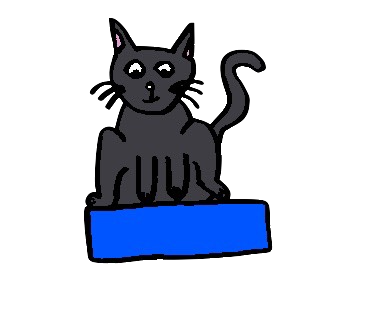
判定分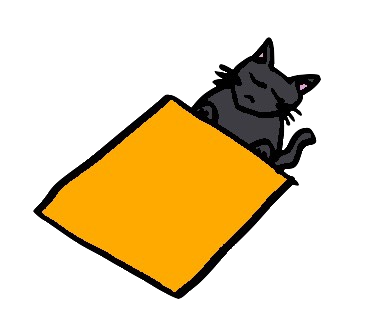
呼び出し
繰り返し
まとめ
約10年IT業界で仕事を続けてこれた理由の1つに今回紹介したフローチャートの存在が間違いなくあります。
今でも複雑なプログラムになったり、想定した動きをしないプログラムの修正中には紙にフローチャートを描いてから作業を進めています。
周りの先輩や後輩でフローチャートを描いている人はほとんどいないと思いますが、わたしはこれをやることで作業効率が格段に上がっていると実感しています。
プログラム初心者の方で躓いた時は、フローチャートを活用してからプログラムを描くことをおすすめします。

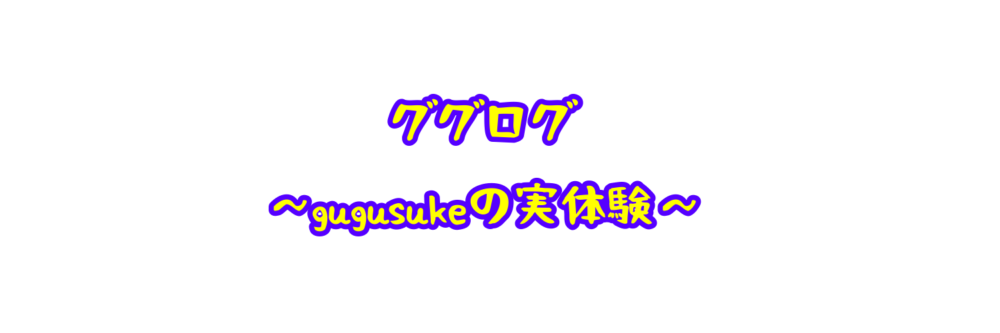
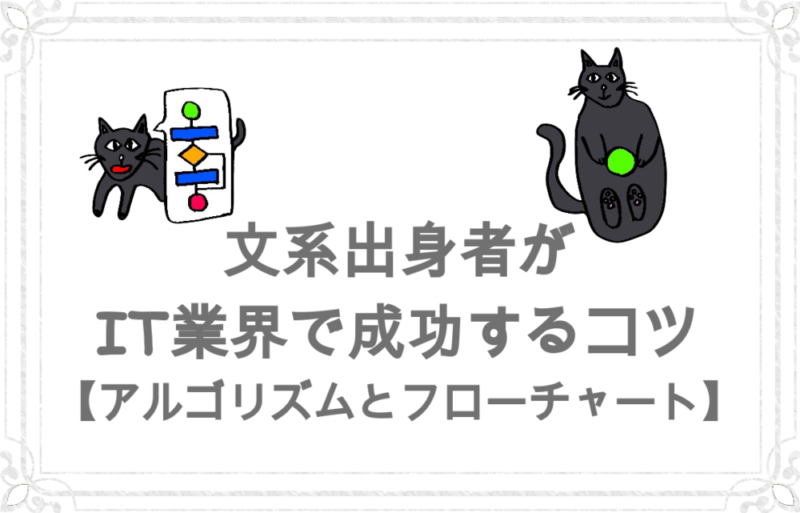
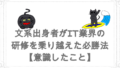
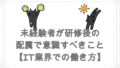
コメント